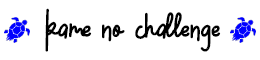鵤、鮴、鮲貝、魦、鳰、鴫、善知鳥、いくつ読めますか?
Posted: || Last Update:

この記事は、漢検100日チャレンジ「100日で漢検一級合格を目指す!漢字の豆知識や日々の進捗をブログで公開」の一環として書かれています。漢字はなるべく正確な情報の記載に努めていますが、間違いがありましたらご連絡いただけると嬉しいです。
目次
漢検一級には不思議生物がいっぱい
本日も亀の歩みで勉強中!こんにちは、「亀の子」です。漢検1級合格を目指す100日チャレンジ63日目になりました。
漢検1級の勉強をしていると、モノ自体をしらない単語がたくさん出てきます。それはもう、たくさん、たくさん、出てきます。そんなわけで、漢字以前に、モノ自体を辞書で引いたり、検索したり、とっても忙しいです!
今日は鳥と魚を中心に調べてみました。この特集なんと10回目です!そして、まだまだストックがあります。何回特集を組んだら全部調べきれるんでしょうか?
以前の特集はこちら!
- 箙、胡簶、袙、花楸樹、胡頽子、虎耳草、皁莢、鳶尾草、金縷梅
- 蘭草、野木瓜、燕子花、虎杖、木賊、大角豆、海蘿、冬青
- 山棟蛇、蛇舅母、鶤鶏、珠鶏、鱠残魚、交喙、冬眠鼠、倍良
- 馬酔木、楮、山桜桃、馬尾藻、黄櫨、満天星、萵苣、草石蚕
- 恙虫、鯎、鮎魚女、聒聒虫、水爬虫、狗母魚、鷦鷯、鮠
- 酢漿草、厚皮香、山小菜、鉄刀木、側金盞花、接骨木、榁、五倍子
- 鶎、鯒、鮗、鱩、天魚、鰍、金襖子、蚊母鳥
- 連枷、澪標、直衣、天蚕糸、梅花皮、障泥、行器、稲架
- 髻華、錏、行縢、魞、簓、籡、筬
正体不明な動物の正体を暴いてみた
今日は鳥を中心に、魚介類も調べてみました。名前は知っていても、姿を知らない生き物もいます!
鵤(いかる)
角のように丈夫な嘴を持つのて「鵤」という字になった「いかる」という鳥。「桑鳲」という書き方もあります。
鳴き声が「イカルコキー」と聞こえるから「いかる」と呼ばれている説がありました。YouTubeで見てみましたが、「イカルコキー」とは聞こえないですね…?
鮴(ごり)
この「鮴」という漢字、ちょっとめんどくさい漢字です。漢検1級には「ごり」とし出てきますが、実は、「めばる」という読み方もされるんです!
メバルはお目目の大きな魚で「春告げ魚」として知られているあの子です。一方の「ごり」は地域によって指す魚が違います。「亀の子」はなぜか「かじか」の別名として知っていました。
ちなみに、「ごりおし」の語源が「ごり」という説もあります。ハゼ科の「ごり」は腹びれで川底に張り付いているため、漁をするときには力をこめて引く必要があります。ここから「ごりおし」が生まれたのかもしれません。
なお、「亀の子」が知っていた「鮴」の別名「鰍(かじか)」については以前の特集でご紹介しています。
関連記事

鶎、鯒、鮗、鱩、天魚、鰍、金襖子、蚊母鳥、、あなたはいくつ知っていますか?漢検1級の漢字には、これまでの人生で見たことも聞いたこともないモノが出てきます。今日はそんな正体不明モノの正体を暴いてみました。
鮲貝(まてがい)
名前は聞いたことがありますが、正体をまったく知らなかった「鮲貝(まてがい)」。「馬刀貝」「蟶貝」とも書きます。画像を開いたら一発で覚えられました。こんな筒形の貝が存在していたとは!
「まて」という名前は、鞘に納めた「馬手差(まてざし)」という短刀に似ていることから来ているそうです。ちなみに「馬手差(まてざし)」は「刺刀(さすが)」の一種だとか…。覚える単語が多い貝です!
魦・𩶗(いさざ)※魚偏に尓
「𩶗(いさざ)」※魚偏に尓。漢字が表記されない方のために、漢字の画像がこちらです。

イサザは「魦」「鱊」「尓魚」とも表記される魚。こちらも名前は聞いたことがありますが、正体を知らなかったので調べてみました。琵琶湖に棲息するハゼの仲間で、黄色い半透明な体をしています。
イサザは、先日ご紹介した「魞(えり)」で漁をするそうです。リンクに魞漁の映像もありますので、よければご参照ください。
関連記事

漢検1級には見たことも聞いたこともない道具がたくさん出てきます。髻華、錏、行縢、魞、簓、籡、筬……、正体不明な道具たちの正体をずばり暴いてみました!あなたはいくつ読めますか?そして、いくつ知っていますか?
鳰(にお)
琵琶湖つながりで、お次は「鳰(にお)」。琵琶湖のことを「鳰の海」と言いますね。「鳰(にお)」はカイツブリのこと。古名の「鳰(にお・にほ)」は「水に入る鳥」が転じたのが由来だとか。
ちなみにカイツブリは「鳰(にお)」のほか、「鸊鷉(へきてい)」「鸊鵜(へきてい)」という言い方もされます。
鴫(しぎ)
こちらも名前は聞いたことがあるけれど…、という鳥「鴫(しぎ)」。白いイメージがあったのですが、雀みたいな模様でした。白いのは「鷺(さぎ)」ですね!「鴫(しぎ)」の模様は雀に似ていますが、形状は「鷺(さぎ)」に近いです。
ちなみに「鴫」は奈良時代にできた国字だそうです。
善知鳥(うとう)
写真を見ると、賢そうな顔をしています。「善知鳥(うとう)」は、血の涙を流して、猟師に捕らえられたわが子を探すことから「善を知る鳥」という漢字が当てられているそうです。
その時の親の鳴き声が「ウトウ、ウトウ」。YouTubeで善知鳥の鳴き声をみると、確かに「ウトウ」と鳴いていました!(1分あたりが分かりやすいです)
今日の勉強の成果
昨日までは模試に取り組んでいましたが、「亀の子」には少し早かったようです。昨日までは模試の見直しにほぼ時間を取られていました…。今日から問題集2冊の勉強にシフトしています!
時間をかけてきちんと漢字を調べられるようになり、学びが多いです。当該漢字を使った熟語などを調べる余裕もできて、試験に役立ちそう!勉強方法を変えた判断は間違っていなかったと思います!
今日の感想
- 誕生の「誕」に惑わされ始めた漢検1級素人、亀の子…
- 「誕」には「うまれる」「いつわる」「おおきい」などの意味がある!
- 「爆誕」、実は「スーパーでたらめ!」という意味ではないかと悩んだりする…
今日もあと一時間ほど勉強したいと思います!では、また明日!