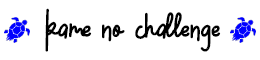蘭草、野木瓜、燕子花、虎杖、木賊、大角豆、海蘿、冬青、漢検1級読めますか?
Posted: || Last Update:

この記事は、漢検100日チャレンジ「100日で漢検一級合格を目指す!漢字の豆知識や日々の進捗をブログで公開」の一環として書かれています。漢字はなるべく正確な情報の記載に努めていますが、間違いがありましたらご連絡いただけると嬉しいです。
目次
漢検一級には不思議植物がいっぱい
こんにちは、亀の歩みでのろのろでも成長中、「亀の子」です。漢字検定1級合格を目指す100日チャレンジ13日目になりました!
漢検1級ってよくわからないモノがたくさん出てきます。11月13日のブログでも、箙、胡簶、袙、花楸樹、胡頽子、虎耳草、皁莢、鳶尾草、金縷梅、などの正体不明なものを紹介しました。あれから5日、また正体不明なモノがたくさんたまってます!
亀の子が世の中のことを知らなさすぎるのか、漢検一級が難しすぎるのか…。そんなわけで「正体不明なモノの正体を暴いてみた」シリーズ第2弾、調べてみたモノの中から植物をご紹介したいと思います!
正体不明な植物の正体を暴いてみた
蘭草(ふじばかま)
蘭草(ふじばかま)は「藤袴」とも書きます。秋の七草の一つらしいです。そんなに有名なのに知らなくてごめんなさい!花が藤色で、花弁が袴のような形をしているので「ふじばかま」なんだって。「蘭草」という書き方は、中国の書き方らしいです。
野木瓜(むべ)
野木瓜(むべ)はアケビの仲間らしいです。「郁子」とも書くとか。「日本では伝統的に果樹として重んじられ、宮中に献上する習慣もある」とwikipediaにありました。高貴な身なんですね~。アケビと比べて実は小さいけれど、甘くておいしいらしい!亀の子も食べてみたい!食い意地で覚えられそうです。
燕子花(かきつばた)
「杜若」と書く方が有名だと思いますが「燕子花」でもカキツバタと読むんですね。花の名前は知っていても、姿を知らなかったので調べてみました。本当だ!燕の子が口を開けてエサを待っている姿に似ています。そういえば、杜若は英語では「Japanese iris」って言うんですよ!(英語を知っているのに正体を知らない不思議…)
虎杖(いたどり)
虎杖(いたどり)は、傷薬として「痛みを取る」から「いたどり」と呼ばれているとか。漢字は、長い茎に虎のような模様があるので「虎杖」と書くらしいです。なるほど~。
ちなみに「虎杖」だけで画像検索をすると、漫画『呪術廻戦』の主人公の画像がたくさん出てきました。そういえばそんな名前でした(斜め読みしてごめん)!植物の方の「虎杖」は「山野や道端、土手などのいたるところで群生」しているらしいです。こちらもメジャーでした…。
木賊(とくさ)
木賊(とくさ)、海賊とか山賊とかの仲間かと思いきや、植物!茎を煮て乾燥させたものを研磨に用いたために「砥草(とくさ)」と呼ばれるようになったのだとか。「木賊」という字は漢名から来ているそうです。
大角豆(ささげ)
大角豆(ささげ)、なんとなく聞いたことがあるような…。でも、分からなかったので調べたら、さやいんげんみたいにして食べていたあれでした!最近スーパーでも見ないな~。空に手を伸ばして物を捧げているように見えるから「ささげ」というようです(諸説あり)。
海蘿(ふのり)
ふのりって、障子の糊に使うあれ?と検索したら、あれでした!もとはこんな姿だったんですね。確かに「海の蘿(つた)」感があります!海蘿から採れる細胞壁多糖「フノラン」はガムの有効成分や健康食品に利用されているらしいです。へぇ~。「布海苔」「布苔」「布糊」という書き方もあります。
冬青(そよご)
冬青(そよご)、常緑樹で冬でも青々と茂っているから「冬青」と書かれるそうです。「そよご」という名前は風に戦(そよ)いで独特な音を立てるところから来ているらしいです。「戦」と一字で書いても「そよご」という植物名になるんですね!
今日の勉強の成果
勉強が進んできて「頻出度順」の難しい所に差し掛かってきたのか、ちょっとペースが落ちてきました…。今日は2時間で昨日までの見直しと、新しいページが2ページしか進んでいません。
焦っても仕方がないのですが、進みが遅いと焦りますね…。「読めるようになった、書けるようになった漢字がたくさんあるじゃないか!」と自分を鼓舞して踏ん張りたいと思います。
今日の感想
- 「海狸」と書いてビーバーなのが納得できない。川にいるし!
- ブログを読み返したら食いしん坊全開だったので、食い意地丸出しの所をかなり削った…
- 削ったのにまだ食いしん坊全開…、どこを削れはいいのか分からないので放置した
今日もあと一時間ほど勉強したいと思います!では、また明日!
▼△▼亀の子が利用している問題集の最新版はこちらから購入できます!